選考辞退を伝えるとき、「LINEで連絡しても大丈夫かな?」と迷う人は少なくありません。
従来はメールや電話が一般的でしたが、最近は採用担当者がLINEを使うケースも増えてきました。
ただし、ビジネスの場である以上、伝え方を誤ると「失礼」と受け止められる可能性もあります。
この記事では、LINEで選考辞退を伝える際の基本マナーや注意点をわかりやすく解説し、状況別にすぐ使えるショート版とフルバージョンの例文をまとめました。
他社内定や一身上の都合、直前辞退など、シーンごとの文例を確認しながら、誠意をもって伝えられる方法を学べます。
「LINEで辞退は失礼では?」という不安を解消し、最後まで印象よくやり取りできるように準備していきましょう。
選考辞退をLINEで伝えても大丈夫?
まず気になるのは「LINEで選考辞退を伝えてもいいの?」という点ですよね。
従来はメールや電話が一般的でしたが、最近はLINEを採用担当者との連絡手段に取り入れる企業も増えています。
ただし、どんな場合でも許されるわけではなく、状況や相手によって適切かどうかが変わります。
LINEで辞退が認められるケースと注意すべきケース
企業がLINEでのやり取りを公式に認めている場合、選考辞退の連絡もLINEで行って問題ありません。
逆に、メールや電話をメインにしている企業に対してLINEで連絡すると、軽く見られる可能性もあります。
「LINEが主要な連絡手段として使われているかどうか」を確認するのが第一歩です。
| ケース | LINEで辞退して良いか |
|---|---|
| 企業がLINEを公式連絡に使っている | 〇 問題なし |
| 企業がメールのみを案内に使っている | △ メールで連絡する方が望ましい |
| 初めての連絡でいきなりLINEを使う | ✕ 避けるべき |
メールや電話との違いと企業側の受け止め方
メールや電話は「形式的で安心感がある手段」と受け止められる一方、LINEは「スピーディーだがカジュアル寄り」と見られることがあります。
そのため、状況によってはLINEよりもメールや電話の方が適切な場合もあります。
大切なのは、相手に失礼のない形で誠意を伝えることです。
選考辞退をLINEで伝える基本マナー
LINEで選考辞退を伝えるときは、ちょっとした工夫で印象が大きく変わります。
ここでは「送るタイミング」「言葉遣い」「送信後のフォロー」の3点を中心に解説します。
送信のタイミングと避けるべきNG例
選考辞退を決めたら、できるだけ早めに連絡するのがマナーです。
直前や当日の連絡は企業側に迷惑をかけるので避けましょう。
最低でも面接の2〜3日前までに伝えるのが目安です。
| タイミング | 評価 |
|---|---|
| 面接の3日前〜前日 | 〇 適切 |
| 面接当日の朝 | △ できれば避けたい |
| 面接開始直前 | ✕ 失礼にあたる |
敬語・文章構成のポイント
LINEは短文になりがちですが、敬語をきちんと使えば誠意が伝わります。
「お世話になっております」から始め、「感謝」「辞退の理由」「お詫び」「結び」の流れを意識すると自然です。
短くても丁寧な文を意識すれば、カジュアルすぎる印象を避けられます。
送信後の対応とフォロー(返信対応・既読スルー時など)
辞退のLINEを送ったあと、企業から返信が来る場合があります。
「ご連絡ありがとうございます」と返されたら、軽く感謝を伝えるのがスマートです。
既読がつかない場合や返信がない場合は、しばらく待ってからメールや電話で補足連絡するのが安心です。
送信後も最後まで礼儀を意識することで印象が良くなります。
状況別・選考辞退のLINE例文集【ショート版】
ここでは、すぐに使える短めの例文を紹介します。
LINEの特性上、文章が長すぎると読みにくいので、シンプルかつ誠意が伝わる内容を意識しましょう。
他社内定が決まった場合の例文(ショート)
お世話になっております。〇〇大学の山田太郎です。
このたび他社への入社を決めましたため、誠に恐縮ですが選考を辞退させていただきます。
これまでご対応いただき誠にありがとうございました。
一身上の都合による辞退の例文(ショート)
お世話になっております。山田太郎です。
誠に勝手ながら、一身上の都合により選考を辞退させていただきたくご連絡いたしました。
貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。
企業とのミスマッチを感じた場合の例文(ショート)
お世話になっております。山田太郎です。
選考を通じて検討した結果、志向と合わない点を感じましたため、辞退させていただきます。
ご理解いただけますと幸いです。
直前の辞退を伝える場合の例文(ショート)
お世話になっております。山田太郎です。
本日の面接ですが、やむを得ない事情により辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。
急なご連絡となり大変申し訳ございません。
インターン・アルバイト選考を辞退する場合の例文(ショート)
お世話になっております。山田太郎です。
このたびはご選考いただきありがとうございます。
誠に恐縮ですが、今回は辞退させていただきます。
| ケース | ショート例文の特徴 |
|---|---|
| 他社内定 | 理由を明確にしつつ感謝を伝える |
| 一身上の都合 | 理由は曖昧でも誠意を示す |
| ミスマッチ | 否定的にならずやんわり伝える |
| 直前の辞退 | お詫びを必ず添える |
| インターン・アルバイト | 簡潔で問題ないが感謝は忘れない |
ショート版は「シンプル+誠意」で伝えるのが成功のコツです。
状況別・選考辞退のLINE例文集【フルバージョン】
こちらでは、冒頭の宛名から結びまで丁寧に書かれた「フルバージョン例文」を紹介します。
形式を整えておけば、どのケースでも誠意が伝わりやすく、社会人としての印象も良くなります。
他社内定が決まった場合のフル例文
〇〇株式会社
人事部 △△様
いつもお世話になっております。〇〇大学の山田太郎です。
このたびは貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。
大変恐縮ですが、他社から内定をいただき、そちらへ進むことを決めました。
誠に勝手ながら、選考を辞退させていただきたくご連絡いたします。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
一身上の都合による辞退のフル例文
〇〇株式会社
人事部 △△様
お世話になっております。〇〇大学の山田太郎です。
このたびは選考の機会をいただき、誠にありがとうございました。
誠に申し訳ございませんが、一身上の都合により辞退させていただきたくご連絡いたしました。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。
貴社の今後のご発展を心よりお祈り申し上げます。
企業とのミスマッチを感じた場合のフル例文
〇〇株式会社
人事部 △△様
お世話になっております。〇〇大学の山田太郎です。
選考の機会をいただき、誠にありがとうございました。
大変恐縮ですが、選考を進める中で、私の志向と貴社の方向性に違いを感じました。
誠に勝手ながら、辞退させていただきたく存じます。
ご理解いただけますと幸いです。
貴社のご発展を心よりお祈りいたします。
直前の辞退を伝える場合のフル例文
〇〇株式会社
人事部 △△様
お世話になっております。〇〇大学の山田太郎です。
本日の面接に関しまして、誠に申し訳ございません。
やむを得ない事情により、急遽辞退させていただきたくご連絡いたしました。
ご多忙の中、日程を調整いただいたにもかかわらず、ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
インターン・アルバイト辞退のフル例文
〇〇株式会社
採用担当 △△様
お世話になっております。〇〇大学の山田太郎です。
このたびはインターン(またはアルバイト)の選考機会をいただき誠にありがとうございました。
恐縮ですが、事情により辞退させていただきたくご連絡いたしました。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
貴社のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。
| ケース | フル例文の特徴 |
|---|---|
| 他社内定 | 感謝+他社決定の明確な理由を伝える |
| 一身上の都合 | 理由をぼかしても誠意ある表現で対応 |
| ミスマッチ | 否定的にならないよう表現をやわらげる |
| 直前辞退 | 強い謝罪を必ず盛り込む |
| インターン・アルバイト | 簡潔ながらも丁寧に感謝を伝える |
フルバージョン例文は「誠意+丁寧さ」で印象を良くする最適解です。
選考辞退をLINEで伝えるメリットとデメリット
LINEで選考辞退を伝えるときには、良い面と注意すべき面の両方があります。
ここでは、メリットとデメリットを整理し、他の連絡手段と比較して解説します。
LINEを使うメリット(スピーディー・手軽さなど)
LINEは普段から使い慣れている人が多く、スピーディーに連絡できるのが大きな利点です。
既読機能により、相手が確認したかどうか分かるのも安心材料になります。
「すぐ伝えたい」「相手もLINEを使っている」場合はメリットが大きいと言えます。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| スピード感 | 送った瞬間に相手へ届き、既読確認も可能 |
| 使いやすさ | 普段から使い慣れているため緊張せずに送れる |
| 柔軟性 | 短文でも長文でも対応可能で状況に合わせやすい |
LINEを使うデメリット(カジュアルさ・誤解のリスクなど)
一方で、LINEは日常的なツールという印象が強く、ビジネスの正式な場では「軽い」と見られることもあります。
また、文章が短すぎると誠意が伝わらず、誤解を招く可能性もあります。
特に「相手がLINEを好まない」ケースでは逆効果になることがあるので注意が必要です。
| デメリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 軽く見られるリスク | 日常ツールのため、ビジネス感に欠ける印象を与える |
| 誤解の可能性 | 短文だと意図が伝わらない場合がある |
| 相手の好みに左右される | メール派の担当者には好印象を持たれにくい |
メールや電話との比較での違い
メールは「正式さ」、電話は「即時性」、LINEは「手軽さ」が特徴です。
どの手段を使うかは、相手が普段どの連絡方法を好んでいるかによって選ぶと良いでしょう。
「相手基準」で手段を選ぶことが円滑な辞退につながります。
企業から返信が来たときの対応例文
選考辞退をLINEで伝えると、担当者から返信をいただくことがあります。
返信が来たときにどのように対応するかで、最後の印象が大きく変わります。
ここでは、状況別に使える返信例文を紹介します。
理解を示された場合の返信例文
担当者から「承知しました」「ご連絡ありがとうございます」といった返信をいただいた場合は、感謝の一言を添えると印象が良くなります。
例文:
ご理解いただきありがとうございます。
貴社のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。
追加の質問が届いた場合の返信例文
辞退理由などを改めて聞かれるケースもあります。
その際は、正直に答える必要はなく、差し障りのない表現で返すのが無難です。
例文:
このたびはご丁寧にご対応いただき誠にありがとうございます。
詳細な理由につきましては個人的な事情によるものですので、何卒ご理解いただけますと幸いです。
返信が不要なケースと対応の仕方
担当者から「承知しました。今後のご活躍をお祈りします。」などで完結している場合は、無理に返信をしなくても問題ありません。
ただし、より丁寧さを重視したい場合は、簡単に感謝を返すのも良い方法です。
例文:
このたびはご丁寧にご返信いただきありがとうございました。
貴社のご発展を心よりお祈り申し上げます。
| 状況 | 対応の仕方 |
|---|---|
| 理解を示された | 一言お礼を返すと印象アップ |
| 追加質問が届いた | 無理に詳細を答えず差し障りのない表現でOK |
| 返信不要の内容 | 返さなくても問題なし、返すなら簡潔に |
最後のやり取りまで丁寧にすることで「印象の良い辞退」を実現できます。
選考辞退をLINEで伝えるときのよくある疑問Q&A
ここでは、実際に多くの人が悩む「LINEでの辞退」に関する疑問をまとめました。
短文での対応や既読機能の扱いなど、ちょっとした工夫で印象を良くすることができます。
既読がつかないときはどうすればいい?
既読がつかない場合、相手がLINEをあまり使っていない可能性があります。
そのまま放置せず、半日〜1日待っても反応がなければメールや電話で補足するのが安心です。
「LINEだけで終わらせない」ことが大切です。
スタンプや絵文字は使ってもいい?
基本的にビジネス連絡ではスタンプや絵文字は避けるべきです。
たとえフランクな雰囲気の担当者であっても、辞退の連絡はフォーマルにまとめましょう。
辞退連絡は「シンプルで丁寧」が鉄則です。
短文で伝えても失礼にならない?
短文でも、感謝・理由・お詫びの3点を含んでいれば失礼にはなりません。
ただし、1行だけの「辞退します」は誠意が伝わらないのでNGです。
最低でも3文程度にまとめると安心です。
夜遅くに送るのは失礼?
ビジネス連絡は相手の勤務時間を意識するのがマナーです。
夜遅くの送信は避け、朝〜夕方の時間帯を選びましょう。
どうしても遅い時間しか送れない場合は、翌日の始業時間に届くように予約送信を活用するのがおすすめです。
| 疑問 | 対応のポイント |
|---|---|
| 既読がつかない | 1日待っても反応がなければ別手段で補足 |
| スタンプや絵文字 | ビジネス連絡ではNG。丁寧な文章を優先 |
| 短文でも大丈夫? | 3文構成(感謝・理由・お詫び)なら問題なし |
| 夜遅い時間帯 | 勤務時間内が基本。どうしてもなら翌朝に届く設定 |
小さな配慮が「誠実さ」として伝わるのがLINE辞退のポイントです。
まとめ|LINEでも誠意を持てば円満に辞退できる
選考辞退をLINEで伝えるのは、場合によっては失礼にあたると感じる人もいます。
しかし、相手がLINEを主要な連絡手段としているなら、丁寧な文章を意識することで問題なく伝えられます。
ポイントは次の3つです。
- 相手の連絡スタイルを尊重すること
- 敬語を使って感謝・理由・お詫びをセットで伝えること
- 送信タイミングや返信対応にも配慮すること
この記事で紹介したショート版・フルバージョンの例文を状況に応じて使い分ければ、スムーズに選考辞退を伝えることができます。
最後まで誠意を持って対応することで、辞退後も良好な関係を保てます。
自分に合った表現を選び、次のステップに向けて前向きに進んでいきましょう。

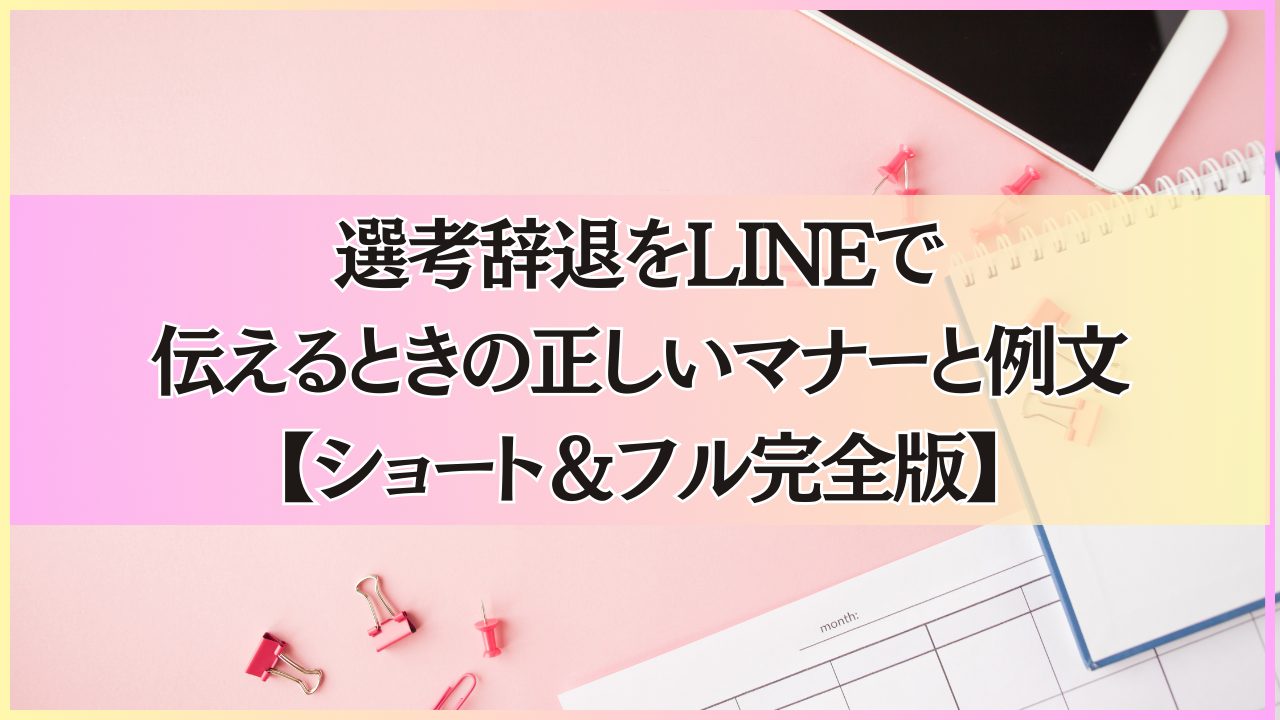
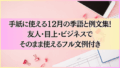
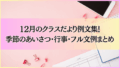
コメント