喪中はがきは、大切な人を亡くした際に「年賀状を控えます」という気持ちを丁寧に伝えるための挨拶状です。
ただ、いざ出そうと思うと「いつ出せばいいの?」「誰に送るべき?」「親戚にも必要?」と迷うことが多いですよね。
この記事では、2025年の最新情報をもとに、喪中はがきを出す最適な時期、送る相手の範囲、親戚への対応マナーまでを分かりやすくまとめました。
初めての方でも安心して準備できるよう、タイミングの目安や文面の基本も紹介しています。
この記事を読めば、「いつ・誰に・どう出すか」がすぐにわかり、失礼のない喪中はがきをスムーズに準備できます。
喪中はがきとは?目的と意味を正しく理解しよう
喪中はがきは、身近な方を亡くした際に新年のご挨拶を控えることをお知らせするための大切な手紙です。
相手に対して礼を失することなく「今年は年賀状を控えます」という気持ちを伝える、思いやりのある日本独自の習慣といえます。
「喪中はがき」と「年賀欠礼状」の違い
喪中はがきは、正式には「年賀欠礼状」と呼ばれることをご存じでしょうか。
これは、新年の祝い事を控えるという意味を持ち、年始の挨拶を差し控える旨を伝える手紙のことです。
つまり喪中はがきは「年賀状を出さない」ための断り状ではなく、「お祝いを控えることへの礼儀」を表す挨拶状なのです。
| 名称 | 目的 |
|---|---|
| 喪中はがき | 喪に服しているため年賀状を控える旨を伝える |
| 年賀欠礼状 | 新年の挨拶を欠くことをお詫びする正式名称 |
なぜ喪中はがきを出す必要があるのか
喪中はがきを出すのは、年賀状をやり取りしている相手への礼儀です。
新年の祝いを受け取る立場にないことを事前に知らせておくことで、相手に余計な気遣いをさせずに済みます。
相手に配慮することが、結果として自分の気持ちを丁寧に伝えることにもつながります。
最近の傾向(メールやLINEで伝えるケースも)
近年では、喪中はがきに代わり、メールやSNSなどを使って喪中を知らせる人も増えています。
ただし、年賀状のやり取りが続いている相手には、従来どおり紙のはがきで送る方が丁寧な印象を与えます。
形式よりも「相手を思う気持ち」を優先して伝えることが最も大切です。
喪中はがきを出す時期はいつ?最も適切なタイミング
喪中はがきを出す時期は、年賀状の準備が始まる前に相手へ届くようにするのが基本です。
タイミングを誤ると、相手が年賀状を準備してしまう可能性があるため、適切な時期に投函することが大切です。
一般的な目安は「11月中旬〜12月上旬」
喪中はがきは、例年11月中旬から12月上旬にかけて投函するのがマナーとされています。
この時期であれば、多くの人が年賀状の印刷や準備を始める前に届くため、相手に十分な配慮ができます。
郵便局の年賀状受付開始は12月15日前後のため、遅くとも12月10日頃までに相手に届くように出すと安心です。
| 投函時期 | 相手に届く目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 11月中旬〜下旬 | 11月末〜12月初旬 | 理想的な時期 |
| 12月上旬 | 12月10日前後 | ギリギリ間に合う |
| 12月中旬以降 | 年賀状作成後に届く可能性 | 寒中見舞いで対応 |
年末や葬儀直後の場合の対応方法
12月中旬以降に不幸があった場合は、喪中はがきを出しても間に合わないことがあります。
その場合は、年始の松の内(1月7日頃)が過ぎてから寒中見舞いとして報告するのが一般的です。
寒中見舞いでは「年末に不幸があり、年賀状を出せなかった旨」を丁寧に伝えると良いでしょう。
早すぎ・遅すぎの注意点と相手への配慮
早すぎる時期(10月以前)に送ると、相手が内容を忘れてしまうことがあります。
逆に遅すぎると、すでに年賀状を作成済みの相手に気を遣わせてしまう可能性も。
「早すぎず、遅すぎず」──11月中旬から12月初旬が最も丁寧で適切なタイミングといえます。
【郵便局最新情報】2025年版・年賀状スケジュール早見表
2025年の年賀状スケジュールを確認しておきましょう。
このスケジュールを参考に、喪中はがきの投函時期を逆算するとスムーズに準備が進みます。
| 項目 | 2025年の目安 |
|---|---|
| 年賀はがき販売開始 | 2024年11月1日 |
| 年賀状引受開始 | 2024年12月15日 |
| 元旦に届くための投函期限 | 2024年12月25日 |
喪中はがきは、相手の年賀状準備スケジュールを意識して出すことが最大のマナーです。
喪中はがきを送る相手の範囲とは?
喪中はがきを送る際に多くの人が悩むのが、「誰に送ればいいのか」という点です。
喪中はがきは、年賀状をやり取りしている人すべてに送るのが基本ですが、関係の深さや状況に応じて対応を調整することも大切です。
基本は「年賀状のやり取りがある人」すべて
喪中はがきは、基本的に年賀状を交換しているすべての相手に送ります。
友人や知人だけでなく、仕事関係者、取引先なども含まれます。
これは、年賀状の受け取りを控える旨を知らせることで、相手に余計な気遣いをさせないためです。
| 送るべき相手 | 送らなくてもよい相手 |
|---|---|
| 年賀状を毎年交換している人 | 普段から年賀状のやり取りがない人 |
| 友人・知人・恩師など | 一度も交流がない人 |
| 取引先やお世話になった関係者 | 一時的な関係で連絡が途絶えている人 |
仕事関係や取引先へのマナーと判断基準
会社の上司や取引先など、業務上のお付き合いがある相手には、基本的に喪中はがきを送る方が丁寧です。
ただし、相手との関係性が形式的な場合や、個人としてではなく会社単位での年賀状交換のみの場合は、省略しても構いません。
「個人としてお付き合いがあるかどうか」を基準に考えると分かりやすいです。
友人・知人・SNSだけの関係の場合はどうする?
最近では、SNSやメールを通じて挨拶を交わす人も増えています。
そうした場合、紙の喪中はがきを送るかどうかは、相手との距離感で判断しましょう。
たとえば、毎年メッセージを送り合う友人であれば、メッセージ上で喪中を伝えるのも一つの方法です。
形式よりも、相手を思いやる伝え方を選ぶことが最も重要です。
親戎に喪中はがきを送るべき?範囲と考え方
親戚への喪中はがきの扱いは、人によって悩みやすいポイントです。
「親族だから送るべきなのか」「お互いに喪中のときはどうするのか」など、判断に迷うことも多いですよね。
ここでは、親戚に対して喪中はがきを出す際の一般的な考え方と、ケース別の対応を解説します。
一般的な「2親等まで」が目安
喪中はがきを送る範囲には明確な決まりはありませんが、一般的には2親等以内の親族を目安とするのが一般的です。
両親、配偶者、子ども、兄弟姉妹、祖父母などがこれに該当します。
つまり、身近な家族に不幸があった場合には、喪中はがきを出す対象と考えましょう。
| 親等 | 関係 | 喪中はがきの対象 |
|---|---|---|
| 一親等 | 両親・配偶者・子ども | 送る |
| 二親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 送るのが一般的 |
| 三親等 | 叔父・叔母・甥・姪 | 関係性により判断 |
同居・別居による違いとケース別対応表
同居している親族と別居している親族では、喪中はがきの対応が異なります。
同居している場合は、すでに喪中であることを互いに承知しているため、喪中はがきを省略しても問題ありません。
一方で別居している兄弟姉妹などには、あらためて知らせる意味で送るのが丁寧です。
| 関係 | 同居・別居 | 対応 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹 | 同居 | 省略しても可 |
| 兄弟姉妹 | 別居 | 送るのが丁寧 |
| 祖父母 | 別居 | 出すのが一般的 |
| 甥姪 | 関係が遠い場合 | 省略しても問題なし |
お互い喪中の場合は省略しても良い?
親戚同士が同じ故人の喪中である場合、喪中はがきを送らないことが一般的です。
たとえば、兄弟や親子など同じ家族内で喪中のときは、すでに事情を共有しているため改めて送る必要はありません。
ただし、離れて暮らしていて最近会っていない場合は、近況報告を兼ねて送るのも丁寧です。
【図解付き】親族関係と喪中対象早見表
以下は、一般的な親族関係と喪中はがきを出す対象をまとめた早見表です。
家族構成や付き合い方に応じて柔軟に判断してください。
| 対象 | 出す目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 両親・配偶者・子ども | 必ず出す | 最も近い関係 |
| 祖父母・兄弟姉妹 | 出すのが望ましい | 別居している場合は特に |
| 叔父・叔母・甥・姪 | 関係性で判断 | 交流が深い場合は出す |
| いとこ・再従兄弟など | 不要 | 年賀状のやり取りがある場合のみ検討 |
親戚への喪中はがきは「義務」ではなく「思いやり」です。相手との関係性を大切にしながら判断しましょう。
喪中はがきを出し忘れた・出せなかった場合の対処法
喪中はがきを出すつもりだったのに、気づけば年末になってしまったということもありますよね。
そんなときに焦って出してしまうと、かえって相手に混乱を与えることもあります。
ここでは、出し忘れたときや出すのが間に合わなかったときの正しい対応方法を紹介します。
寒中見舞いで丁寧にフォローする方法
喪中はがきを出す時期を逃してしまった場合は、年明けに寒中見舞いとしてご挨拶を出すのが一般的です。
寒中見舞いは、松の内(1月7日頃)を過ぎてから立春(2月4日頃)までに送る季節の挨拶状です。
年末に不幸があった場合や、喪中はがきを出す余裕がなかった場合でも、寒中見舞いなら丁寧にお知らせできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送る時期 | 1月8日〜2月4日頃 |
| 目的 | 喪中を知らせる・お詫び・近況の挨拶 |
| 文例の一例 | 「昨年末に身内に不幸があり、新年のご挨拶を控えさせていただきました」 |
すでに年賀状を受け取ってしまった場合の返礼文例
喪中であることを伝える前に年賀状を受け取った場合も、慌てる必要はありません。
この場合も寒中見舞いとして返信すれば大丈夫です。
以下のような文例を参考にしてみましょう。
例文:
お年賀のご挨拶をありがとうございました。
昨年○月に○○が他界いたしましたため、年末年始のご挨拶を控えさせていただきました。
ご連絡が行き届かず申し訳ございませんでした。
本年も変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます。
出し忘れた場合の「お詫びと説明」の書き方
喪中はがきを出しそびれた場合、後から出す際には「遅れたことへのお詫び」を一言添えると丁寧です。
たとえば、「ご連絡が遅くなりましたが、喪に服しておりますため年始のご挨拶を控えさせていただきます」と記すと誠意が伝わります。
大切なのは、形式よりも気持ちを込めて丁寧に伝えることです。
喪中はがきの書き方・デザイン・切手マナー
喪中はがきは、内容だけでなく見た目の印象や文面の言葉づかいも大切です。
ここでは、喪中はがきを準備する際に押さえておきたい基本マナーと、文面やデザインの注意点を紹介します。
文章構成の基本と避けるべき言葉
喪中はがきの文面には、一般的な構成があります。
形式を守りながらも、やわらかく心を込めて書くことが大切です。
| 構成部分 | 内容 |
|---|---|
| ①冒頭 | 「喪中につき新年のご挨拶を控えさせていただきます」と伝える |
| ②故人について | 亡くなった方の続柄・時期・感謝の言葉などを簡潔に記す |
| ③締めの言葉 | 「本年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます」などで結ぶ |
また、喪中はがきでは「賀」「寿」「福」といったお祝いを連想させる言葉は避けるのがマナーです。
句読点も使わずに、丁寧で落ち着いた文面を意識しましょう。
差出人が複数(夫婦・家族)の場合の書き方
夫婦や家族連名で喪中はがきを出す場合は、誰の関係で喪中なのかを明確に記載します。
たとえば、夫婦連名で出す場合には「義母○○が他界いたしました」などと書くと丁寧です。
家族それぞれで出す場合には、差出人の名前ごとに関係を分けて書くのが自然です。
家族単位での喪中はがきは、代表者名を中心に記載し、他の家族名を添える形が一般的です。
官製・私製はがきの違いと弔事用切手の選び方
喪中はがきには、郵便局で販売されている官製はがきと、自分で購入する私製はがきの2種類があります。
官製はがきはすぐに使用できるため便利ですが、私製はがきを使用する場合は弔事用の切手を貼るのがマナーです。
郵便局で「弔事用63円切手」を購入すると、落ち着いたデザインで上品な印象になります。
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 官製はがき | 切手印刷済み・すぐ使用可能 | 弔事デザインを選ぶ |
| 私製はがき | 自由なデザインが可能 | 必ず弔事用切手を貼る |
近年人気のデザイン傾向と注意点
最近では、従来の白黒だけでなく、蓮の花や柔らかな色合いを取り入れた喪中はがきも増えています。
文字の色を薄墨風にしたり、背景に淡い模様を入れることで、上品で落ち着いた印象を与えられます。
派手になりすぎない範囲で、自分らしさや故人への想いを表現するデザインを選ぶと良いでしょう。
喪中はがきを出す前に確認したいチェックリスト
喪中はがきを出す時期や相手、文面の準備が整っても、いざ出す前に見落としがちなポイントがあります。
ここでは、喪中はがきを出す直前に確認すべき内容を一覧にまとめました。
出す時期・相手・文面の最終確認
喪中はがきを投函する前に、まず以下の3点をチェックしておきましょう。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 時期 | 11月中旬〜12月上旬に投函しているか |
| 相手 | 年賀状を交換している人全員に送っているか |
| 文面 | 句読点やお祝いの言葉が入っていないか |
たった一文字の誤字や言葉遣いの違いが、印象を左右します。
印刷前に読み返し、できれば家族にも確認してもらいましょう。
出し忘れを防ぐ準備スケジュール表
スムーズに喪中はがきを準備するためには、早めのスケジュール管理が欠かせません。
以下のようなスケジュールを参考にして、余裕を持った準備を心がけましょう。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10月下旬 | 喪中はがきのデザインを選ぶ・住所録を整理 |
| 11月上旬 | 文面を決めて印刷を依頼 |
| 11月中旬 | 印刷されたはがきを確認し投函準備 |
| 12月上旬 | 最終確認のうえ投函 |
喪中はがきは「直前に慌てて作る」よりも「計画的に準備する」ことで、相手への配慮が自然に伝わります。
寒中見舞い・再開の挨拶を見据えた対応
喪中が明けた後には、寒中見舞いや新年の挨拶を再開するタイミングも考えておくとスムーズです。
喪中はがきを出す際に住所録を整理しておくと、次の季節の挨拶状を準備する際に役立ちます。
喪中の期間は終わりではなく、故人を想いながら少しずつ日常を整える時間でもあります。
まとめ|思いやりを伝える喪中はがきで丁寧なご挨拶を
ここまで、喪中はがきの出す時期・相手の範囲・親戚への対応・書き方の基本などを解説してきました。
喪中はがきは形式的なマナーではなく、相手への思いやりを形にする大切な挨拶状です。
マナーを守ることは心を伝えること
喪中はがきを送ることで、「年賀状を控えます」という事実だけでなく、「気遣いの心」を伝えることができます。
故人を偲びつつ、相手への感謝と丁寧な気持ちを文面に込めることが、最も重要なポイントです。
形式よりも心を込めた一枚が、相手にとっても温かく印象に残るご挨拶になります。
喪中明け後の挨拶で関係を温かくつなぐ
喪中が明けた後は、寒中見舞いや次の年の年賀状で新たなご挨拶を交わすことで、関係をつなぎ直す良い機会になります。
久しぶりに年賀状を再開する際は、「ご無沙汰しております」「お変わりなくお過ごしでしょうか」といった一言を添えると自然です。
喪中はがきも寒中見舞いも、どちらも人との絆を大切にするためのツール。
思いやりのある言葉を通じて、静かで穏やかな新年を迎えましょう。

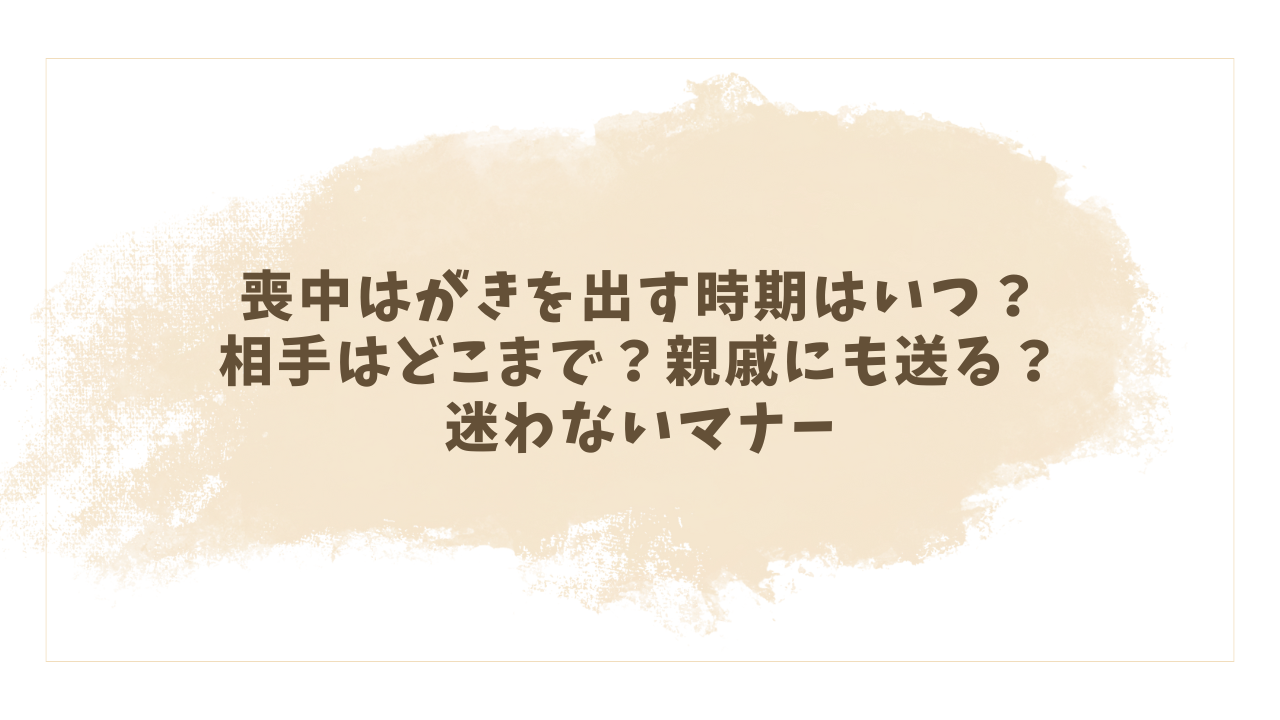
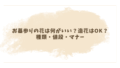
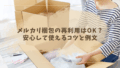
コメント