親戚からお歳暮をいただいたとき、「どんなお礼状を書けばいいのかな」と迷う方は少なくありません。
感謝の気持ちを伝えるだけでなく、親戚との絆を深める大切な役割を持つのがお礼状です。
この記事では、2025年の最新マナーをふまえつつ、親戚に喜ばれるお礼状の書き方を解説します。
シンプルにまとめたいときの短文、親しみを込めたカジュアルな一文、義理の親戚にも安心して送れるフォーマルな文例まで、豊富な例文を用意しました。
さらに、頭語から結語まで整ったフルバージョンの完成例文も掲載しているので、そのまま便箋に書き写して使うこともできます。
「心を込めて書きたいけれど、言葉にするのが難しい」という方にこそ役立つ内容です。
これ一つで、親戚へのお歳暮お礼状がすぐに書けるようになります。
親戚にお歳暮をいただいたらお礼状は必要?
お歳暮を受け取ったときに「お礼状ってわざわざ必要かな?」と迷う方は多いですよね。
この章では、親戚からのお歳暮に対してお礼状を出す意味や、その背景をわかりやすく解説します。
出さないとどう思われる?最新マナーの考え方
親戚からのお歳暮は、単なる贈り物ではなく「これからもつながりを大事にしています」という気持ちの表れです。
そのためお礼状を出すことは、相手の気持ちに応える一番シンプルな方法だといえます。
出さなかったからといってすぐに関係が悪くなるわけではありませんが、心の中で「少しさみしいな」と思われる可能性はあります。
特に親戚との間柄では、礼儀そのものよりも「気にかけてくれているんだな」という安心感が大切です。
| お礼状を出す場合 | 出さない場合 |
|---|---|
| 丁寧で誠実な印象を与えられる | 受け取ったことが伝わらず不安にさせる可能性 |
| 関係性を温かく保ちやすい | 距離があると感じさせてしまう |
親戚ならではの気遣いと距離感
ビジネス相手と違い、親戚へのお礼状は形式的すぎなくても問題ありません。
むしろ堅苦しすぎる文面は、かえって距離を感じさせてしまうこともあります。
「贈り物をいただいてうれしかった」「みんなで楽しんだ」というような素直な言葉が一番伝わります。
親戚だからこそ、家族的な温かさを感じられるお礼状が喜ばれるのです。
お歳暮のお礼状はいつまでに出すべき?
お歳暮をいただいたら、できるだけ早めにお礼状を送るのが基本です。
ここでは「いつまでに出せばいいのか」「遅れてしまったらどうすればいいのか」を具体的にまとめます。
理想は3日以内・遅れたときの対応例
お礼状は受け取ってから3日以内に投函するのが理想です。
早ければ早いほど「きちんとしているな」と感じてもらえます。
もし3日以内に間に合わなくても、1週間以内であれば失礼には当たりません。
さらに遅れてしまった場合は、まず電話やLINEで「届きました、ありがとうございます」と一言伝え、その後で手紙を出すと安心です。
| 対応時期 | おすすめの対応方法 |
|---|---|
| 3日以内 | お礼状をすぐに投函 |
| 1週間以内 | 通常の範囲内としてお礼状を出す |
| 1週間以上遅れた | 電話やLINEで先に感謝を伝え、後からお礼状 |
電話・LINE・手紙はどう使い分ける?
近年はSNSやメールで済ませる人も増えていますが、親戚宛の場合はやはり直筆のお礼状が一番印象に残ります。
ただし、連絡手段をうまく組み合わせるのも現代的です。
たとえば「受け取りました、ありがとうございます」とLINEで伝え、その後あらためて手紙を送ると、形式と温かさの両方が伝わります。
親戚との関係性に合わせて、手紙とデジタルを柔軟に使い分けるのが今のマナーです。
親戚へのお礼状の基本マナーと構成
親戚に送るお礼状は、ビジネス文のようにかしこまった形よりも、家庭的な温かさを感じさせることが大切です。
この章では、親戚向けのお礼状に入れるべき基本的な要素と、その書き方のコツを紹介します。
冒頭の季節の挨拶の書き方例
お礼状はまず「季節の挨拶」で始めるのが定番です。
冬ならではのフレーズを入れると、より丁寧に感じられます。
例えば以下のような書き出しが使えます。
| フォーマル | 親しみやすい |
|---|---|
| 「師走の候、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか」 | 「寒い日が続きますが、いかがお過ごしですか」 |
感謝の気持ちと贈り物の感想を伝えるコツ
お歳暮をいただいたことに対する感謝をはっきり伝えることが大切です。
加えて、品物に触れて感想を書くと、受け取った側は「喜んでもらえたんだ」と安心します。
「美味しくいただきました」「家族で楽しく分け合いました」などの一文は必須です。
感謝+具体的な感想、これが基本の流れです。
| 感謝の表現 | 具体的な感想 |
|---|---|
| 「ご厚意をいただきありがとうございます」 | 「食卓が明るくなりました」 |
| 「お心遣いに感謝申し上げます」 | 「家族で楽しくいただいております」 |
相手の健康や家族を気遣う一言の例
親戚宛てのお礼状では、最後に相手を思いやる言葉を添えると文章がやわらぎます。
「寒さが続きますのでご自愛ください」「よい年をお迎えください」などが一般的です。
読み手を気遣う一文を入れると、形式的ではなく心のこもったお礼状になります。
| フォーマル | 親しみやすい |
|---|---|
| 「年末に向けてご多忙のことと存じますが、どうぞご自愛ください」 | 「寒い日が続きますので、あたたかくしてお過ごしくださいね」 |
親戚に喜ばれる表現フレーズ集
親戚へのお礼状は、相手との関係性に合わせた言葉を選ぶと、より自然で温かい印象になります。
ここでは、叔父・叔母、いとこ、義理の親戚など、シーン別に使いやすいフレーズを紹介します。
叔父・叔母に適した表現
目上の立場になることが多いため、やや丁寧さを意識した表現が安心です。
かしこまりすぎず、落ち着いたトーンがちょうどよいでしょう。
| 感謝の言葉 | 合わせる一文 |
|---|---|
| 「結構なお品をいただき、誠にありがとうございます」 | 「ご厚意に心から感謝申し上げます」 |
| 「温かいお心遣いに御礼申し上げます」 | 「おかげさまで家族一同ありがたく頂戴しております」 |
いとこ宛てのカジュアル表現
年齢が近い場合は、少しくだけた言葉でも大丈夫です。
ただし「ありがとう」だけで終わらず、一言添えるのがポイントです。
| カジュアル表現 | 添える一文 |
|---|---|
| 「素敵なお歳暮をありがとう」 | 「早速みんなでいただきました」 |
| 「とても嬉しかったよ」 | 「気持ちがほっこりしました」 |
義理の親戚宛ての丁寧表現
義理の関係は「親しさ」と「礼儀」のバランスが大切です。
丁寧な敬語を基本にしながら、柔らかさを意識して書くと好印象です。
| 丁寧な表現 | 補足の一文 |
|---|---|
| 「このたびはご厚情を賜り、誠にありがとうございます」 | 「ありがたく拝受いたしました」 |
| 「心のこもったお品を頂戴し、深く感謝申し上げます」 | 「家族でありがたく頂戴しております」 |
相手との関係性に応じて言葉を調整することが、親戚宛のお礼状を成功させるコツです。
親戚宛のお歳暮お礼状の例文集【そのまま使える】
ここからは、実際にそのまま使えるお礼状の例文を紹介します。
親戚との関係性や距離感に合わせて、シンプル・カジュアル・フォーマルの3パターンを用意しました。
シンプルで短めの例文(2〜3文)
まずは最低限の感謝を伝える、短くてシンプルな例文です。
叔父・叔母宛てなど、ほどよく丁寧にしたいときに便利です。
| 例文 |
|---|
| 「このたびはご丁寧なお心遣いをいただき、誠にありがとうございます。 家族みんなでありがたく頂戴しました。 寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください。」 |
親しみを込めたカジュアル例文
いとこ宛てなど、親しさを出したい場合はこちらがおすすめです。
気持ちを素直に書くだけで、十分に伝わります。
| 例文 |
|---|
| 「素敵なお歳暮をありがとう。 早速みんなでいただき、食卓がとても明るくなりました。 また会える日を楽しみにしています。」 |
丁寧でフォーマルな例文
義理の親戚や年長者に送るときは、フォーマルさを意識した文面にすると安心です。
相手に敬意を示しつつも温かさを忘れないのがポイントです。
| 例文 |
|---|
| 「拝啓 師走の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 このたびは結構なお歳暮の品を賜り、誠にありがとうございました。 ご厚意に心より御礼申し上げます。 年の瀬に向けてお忙しいことと存じますが、どうぞおだやかな新年をお迎えください。 敬具」 |
フルバージョンの完成例文【頭語〜結語まで】
ここでは、実際の手紙形式で頭語から結語まで整った文例をご紹介します。
叔父・叔母、いとこ、義理の親戚宛ての3パターンを用意しました。
叔父・叔母宛に送る丁寧文例
| 例文 |
|---|
| 拝啓 年の瀬の候、いかがお過ごしでしょうか。 このたびは心のこもったお歳暮をお送りいただき、誠にありがとうございました。 家族一同、ありがたく頂戴し、楽しく味わわせていただいております。 お心遣いに重ねて御礼申し上げます。 寒さが一段と厳しくなってまいりましたので、どうぞお体を大切にお過ごしください。 来る年がより良い一年となりますようお祈り申し上げます。 敬具 |
いとこ宛に送るカジュアル文例
| 例文 |
|---|
| こんにちは。 このたびは素敵なお歳暮をありがとう。 みんなで早速いただき、とても楽しい気持ちになりました。 離れて暮らしていても、こうして思ってもらえることが嬉しいです。 また近いうちに会えるといいね。 新しい年もどうぞよろしくお願いします。 |
義理の親戚宛に送る正式文例
| 例文 |
|---|
| 拝啓 師走の候、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。 このたびはご丁寧にお歳暮をお贈りいただき、誠にありがとうございました。 ご厚意に深く感謝申し上げますとともに、ありがたく拝受いたしました。 頂戴いたしました品は、家族そろって大切にいただいております。 年末のお忙しい時期かと存じますが、どうぞご自愛のうえ、よいお年をお迎えください。 来年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。 敬具 |
頭語から結語まで整った形にしておくと、そのまま便箋やハガキに書き写して送れるので安心です。
さらに心が伝わるお礼状の工夫
お礼状は感謝を伝えるだけでなく、「あなただからこそ送った特別な一通」に仕上げることで、より印象に残ります。
ここでは、簡単に取り入れられる工夫を紹介します。
近況報告を添える書き方
親戚宛てのお礼状では、贈り物への感謝に加えて近況を少し伝えると温かみが増します。
「子どもが元気に過ごしています」「仕事が落ち着きました」など、短い一文で十分です。
相手も自分のことを思い出しやすくなり、話題のきっかけにもなります。
| 工夫の例 | 添えるフレーズ |
|---|---|
| 家族の話題 | 「子どもたちも元気にしています」 |
| 暮らしの様子 | 「こちらは冬支度も整い、落ち着いて過ごしています」 |
写真や年賀状と組み合わせるアイデア
年末年始にお礼状を送る場合、年賀状や写真を同封するのもおすすめです。
近況を視覚的に伝えられるため、文字だけの手紙よりもぐっと親しみが増します。
「贈り物+メッセージ+写真」で三倍気持ちが伝わると考えるとよいでしょう。
便箋・はがき選びで印象を変える
同じ文章でも、どんな便箋やはがきを使うかで印象は大きく変わります。
冬らしい雪の柄や、落ち着いた和紙風のデザインを選ぶと、季節感が出てより丁寧に感じられます。
逆に、いとこ宛てなど親しみを込めたいときは、カジュアルな絵柄入りのはがきも良いでしょう。
| 送り先 | おすすめの便箋・はがき |
|---|---|
| 叔父・叔母 | 和紙風や無地で落ち着いたデザイン |
| いとこ | イラスト入りやカジュアルなはがき |
| 義理の親戚 | シンプルで清潔感のある便箋 |
2025年版 お歳暮とお礼状の最新傾向
ここ数年でお歳暮やお礼状のスタイルには変化が見られます。
2025年の最新傾向を押さえておくことで、親戚へのお礼状にも自然に取り入れられます。
親戚に喜ばれる贈り物のトレンド
最近は高級品よりも「気軽に楽しめる日常の品」が選ばれることが多くなっています。
お菓子や調味料、生活を彩る小物などが人気で、相手が気を使わず受け取れる点がポイントです。
重さよりも「気持ちのこもった実用的な贈り物」が主流になっています。
| 以前の主流 | 最近の傾向 |
|---|---|
| 高級食材や高価なギフト | 日常で使いやすい食品や小物 |
| 量が多く豪華なセット | 少量でも質がよく手軽に楽しめるもの |
デジタルお礼状の広がりと注意点
メールやLINEでお礼を伝えるスタイルも定着しつつあります。
ただし、親戚に対してはデジタルだけでは素っ気なく感じられる場合もあります。
ベストなのは「まずLINEで受け取った報告→後日お礼状」という二段階のやり取りです。
スピード感と温かさの両方を届けられるのが魅力です。
「形式より気持ち」が重視される背景
2025年のいま、形式にとらわれすぎないお礼状が主流になっています。
決まり文句を並べるよりも、自分の言葉で感謝や嬉しさを伝えることのほうが大切にされています。
親戚宛てでは特に「心のこもった一文」が信頼関係を深めるカギとなります。
まとめ:親戚に喜ばれる心温まるお礼状とは
親戚からいただいたお歳暮へのお礼状は、単なる形式的なマナーではなく、家族としてのつながりを深める大切な機会です。
この記事で紹介したように、お礼状には「感謝」「贈り物への感想」「相手を思いやる一言」の3つを盛り込むのが基本です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 感謝 | 「このたびはありがとうございます」とはっきり伝える |
| 感想 | 「家族で楽しくいただきました」など具体的な一文を添える |
| 気遣い | 「よいお年をお迎えください」など温かい言葉を入れる |
また、叔父・叔母には丁寧に、いとこにはカジュアルに、義理の親戚にはフォーマルにと、相手に合わせて言葉を調整することも大切です。
相手の顔を思い浮かべながら一文一文を書くだけで、心のこもったお礼状になります。
2025年の最新傾向としてデジタルも広がっていますが、親戚に対してはやはり手書きのお礼状が一番気持ちを伝えやすいです。
ぜひ今回の例文を参考に、あなたらしい言葉でお礼状をしたためてみてください。

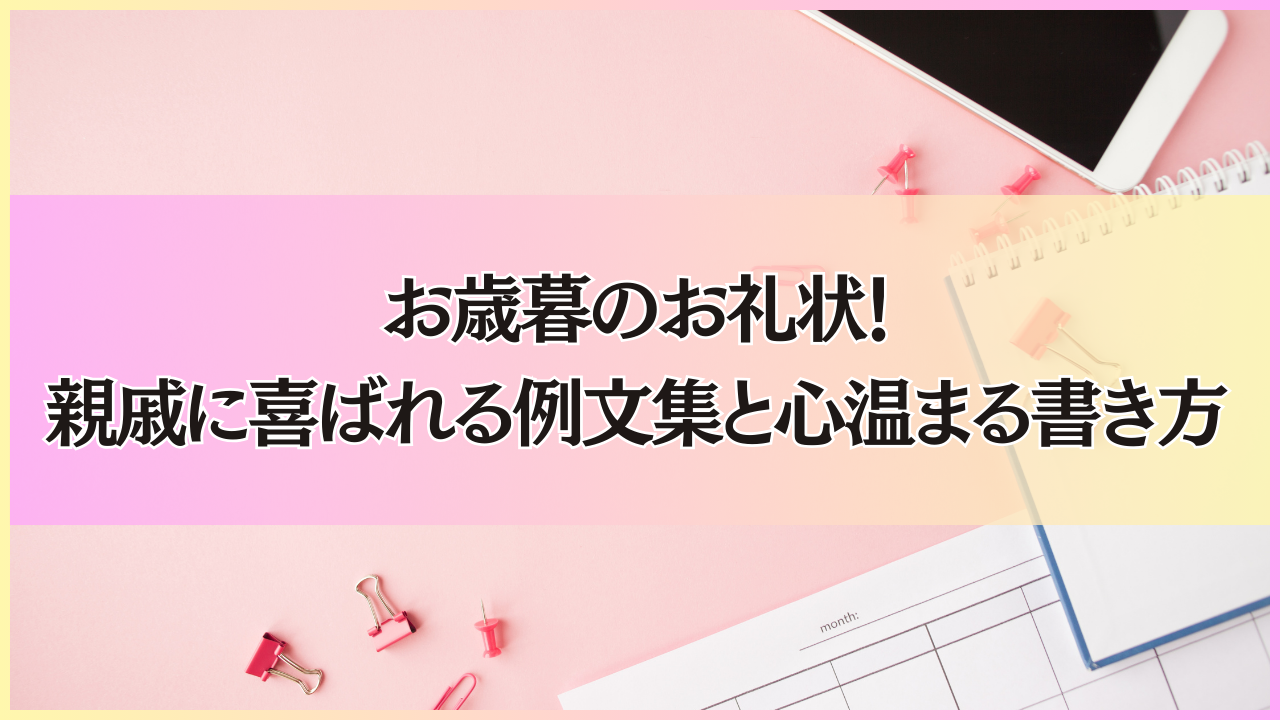
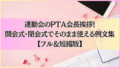
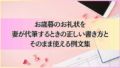
コメント