小学校の連絡帳で「早退の連絡」を書くとき、どんな言葉を選べばいいのか迷ったことはありませんか。
伝えたいのはシンプルなことでも、先生にしっかり伝わるように書くには、ちょっとしたコツが必要です。
この記事では、「小学校 連絡帳 早退 例文」という検索意図に沿って、家庭の事情や通院などの理由別にすぐ使える文例を20種類紹介。
さらに、丁寧で印象の良い書き方・NG表現の言い換え・テンプレートまで完全網羅しています。
この記事を読めば、どんな場面でも自信を持って早退の連絡が書けるようになります。
スマホからでもすぐ使える例文付きなので、忙しい朝にも便利です。
小学校の連絡帳で早退を伝える基本マナーと考え方
早退の連絡は、学校との信頼関係を築く上でとても大切な場面です。
連絡帳はちょっとしたメモではなく、「家庭と先生をつなぐ正式な記録」として扱われます。
ここでは、正しく・丁寧に伝えるための基本マナーと考え方を整理します。
連絡帳は「家庭と先生をつなぐ公式文書」
小学校の連絡帳は、子どもを中心に家庭と学校をつなぐ大切なツールです。
特に早退の連絡は、先生が当日の予定を調整したり、安全な引き渡しを行うために必要な情報です。
つまり、連絡帳は「口頭でのお願い」ではなく「正式な依頼文書」としての意味を持ちます。
そのため、短い文でも敬意と正確さを忘れないことが大切です。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 本日〇時頃に早退させていただきます。お迎えは母が参ります。 | 今日は帰ります。よろしく。 |
早退連絡で欠かせない3要素(理由・時間・迎え)
連絡帳に早退の記載をする際は、必ず以下の3点を明記しましょう。
- 理由: 先生が理解できる程度の簡潔な説明(家庭の都合など)
- 時間: 「○時頃」または「○時間目から」など明確な表現
- お迎え: 誰が、どこへ迎えに来るのかを具体的に書く
この3つの情報が揃っていないと、先生が判断に迷ってしまう可能性があります。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 理由 | 家庭の都合で |
| 時間 | 14時頃に |
| お迎え | 母が正面玄関に伺います |
書く前に押さえたい!先生が読みやすい連絡帳のコツ
先生が一日に目を通す連絡帳は数十冊にのぼることもあります。
そのため、文字の丁寧さと情報の順番がとても重要です。
まずは「一文一情報」でシンプルにまとめることがポイントです。
また、「いつもお世話になっております」から始めると、読み手への印象も柔らかくなります。
| ポイント | 例文 |
|---|---|
| 書き出し | いつもお世話になっております。 |
| 要件 | 本日〇時頃に早退させていただきます。 |
| 補足 | お迎えは母が参ります。よろしくお願いいたします。 |
このように、3文で完結する書き方が最も伝わりやすく、先生も確認しやすい構成です。
書き慣れていない方は、後述のテンプレート例文を参考にすると安心です。
早退の連絡は「短く、正確に、丁寧に」が鉄則です。
【完全保存版】小学校の連絡帳・早退例文集(シーン別20選)
ここでは、小学校の連絡帳に書ける早退の例文をシーン別に紹介します。
短くまとめたい方にも、ていねいに書きたい方にも使えるように、さまざまな文例を用意しました。
そのまま書き写せる実用的な例文を中心に構成しています。
体調不良による早退の例文(軽めのケース)
子どもの様子を簡潔に伝えるシンプルな文面です。
| 目的 | 例文 |
|---|---|
| 短くまとめたい場合 | いつもお世話になっております。本日〇時頃に早退させていただきます。お迎えは母が伺います。 |
| ていねいに伝えたい場合 | いつもお世話になっております。本日、子どもの体調が優れないため、〇時頃に早退させていただきます。お迎えは私が参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 |
病院・通院のために早退する場合の例文
あらかじめ予定が決まっている早退の伝え方です。
| 目的 | 例文 |
|---|---|
| 定期的な通院 | いつもお世話になっております。本日は通院のため、〇時間目終了後に早退させていただきます。お迎えは父が伺います。よろしくお願いいたします。 |
| 午後に用事がある場合 | いつもお世話になっております。本日午後、家庭の用事があるため、〇時頃に早退させていただきます。お迎えは母が参ります。 |
家庭の都合による早退の例文(冠婚・行事など)
家庭の事情を丁寧に伝えるときの書き方です。
| 目的 | 例文 |
|---|---|
| 家庭の事情(一般) | いつもお世話になっております。本日〇時頃、家庭の事情により早退させていただきます。お迎えは祖母が伺います。どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 冠婚関連 | いつもお世話になっております。本日は家庭の行事のため、〇時間目で早退させていただきます。お迎えは父が伺います。よろしくお願いいたします。 |
| 家庭での予定 | いつもお世話になっております。本日、家庭の都合により〇時に早退させていただきます。お迎えは母が参ります。 |
天候や安全面への配慮による早退の例文
天候の変化や安全上の理由で早退させる際の文面です。
| 目的 | 例文 |
|---|---|
| 天候の変化に備えて | いつもお世話になっております。本日は天候の影響が心配なため、〇時頃に早退させていただきます。お迎えは母が伺います。 |
| 安全を優先する場合 | いつもお世話になっております。本日は下校時の安全を考慮し、〇時間目終了後に早退させていただきます。お迎えは父が伺います。 |
急な予定変更や突発的な早退の例文
予期しない事情が発生したときの丁寧な書き方です。
| 目的 | 例文 |
|---|---|
| 急な予定が入った場合 | いつもお世話になっております。急な家庭の都合により、本日〇時頃に早退させていただきます。お迎えは母が参ります。よろしくお願いいたします。 |
| 学校中で連絡したい場合 | いつもお世話になっております。本日、予定の変更により〇時頃に早退させていただきます。お迎えは父が伺います。どうぞよろしくお願いいたします。 |
【フルバージョン例文】正式な書き方モデル
少し長めでも、先生への配慮を十分に含めた「丁寧で完璧な文例」です。
学校行事や担任への信頼関係を重視したいときにおすすめです。
| 目的 | 例文 |
|---|---|
| 正式な連絡文 | いつもお世話になっております。 本日〇月〇日(〇曜日)は、家庭の事情により〇時間目で早退させていただきたく存じます。 お迎えは母が正面玄関に伺います。 ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
この例文は、敬意・具体性・読みやすさの3要素をすべて満たしています。
特に「〇月〇日」「〇時間目」「お迎えの場所」を明記することで、誤解を防ぐことができます。
これらの例文をベースに、次の章では「テンプレート形式」で自分の状況に合わせて簡単に書ける方法を紹介します。
連絡帳で伝わる!好印象な書き方・文例テンプレート
ここでは、早退をスムーズに伝えるための「好印象な書き方」と「すぐ使えるテンプレート」を紹介します。
どんなシーンでも安心して使えるように、短文・中文・正式文の3段階で整理しました。
大切なのは“ていねいさ”と“分かりやすさ”のバランスです。
「いつ」「誰が」「どこで」を自然に入れる方法
早退を伝える際は、3つの情報を順番に書くことで読みやすくなります。
| 順番 | 内容 | 例文 |
|---|---|---|
| ①いつ | 日付・時間を明確に書く | 本日〇月〇日(〇曜日)〇時頃 |
| ②誰が | お迎えに来る人を具体的に | お迎えは母が伺います |
| ③どこで | 迎えの場所を明記 | 正面玄関で待っています |
この3つを入れるだけで、連絡文の信頼度がぐっと上がります。
省略せずに記載することが、先生への配慮につながります。
簡潔だけど失礼のない言葉遣い例
丁寧すぎると堅苦しくなり、くだけすぎると失礼に見えることもあります。
ここでは、印象を良くする「ちょうどいい言葉遣い」をまとめました。
| 避けたい表現 | おすすめの言い換え |
|---|---|
| 〜で帰ります | 〜のため、早退させていただきます |
| すみませんが | お手数をおかけしますが |
| よろしくです | よろしくお願いいたします |
短い文章でも、敬語をきちんと整えるだけで印象が変わります。
“お願い”よりも“依頼”のトーンを意識すると、読み手に好印象を与えます。
【テンプレート集】そのまま使える3パターン(短文/中文/正式文)
ここでは、実際にそのまま使える形で3つのテンプレートを用意しました。
| タイプ | テンプレート例文 | 特徴 |
|---|---|---|
| 短文タイプ(30秒で書ける) | いつもお世話になっております。 本日〇時頃に早退させていただきます。 お迎えは母が伺います。 よろしくお願いいたします。 |
短くても要点をしっかり伝えられる定番スタイル |
| 中文タイプ(少し丁寧に伝える) | いつもお世話になっております。 本日〇月〇日(〇曜日)は、家庭の都合により〇時間目終了後に早退させていただきます。 お迎えは父が正面玄関に伺います。 お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
日付や理由を入れてより具体的に伝えたいときに最適 |
| 正式文タイプ(フォーマルで信頼感のある書き方) | いつもお世話になっております。 本日〇月〇日(〇曜日)は、家庭の事情により〇時頃に早退させていただきたく存じます。 お迎えは祖母が伺います。 ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
担任や学年主任に見られても安心な丁寧表現 |
状況や時間の都合に応じて、上記のテンプレートをそのまま使い分けるのがおすすめです。
どのパターンでも、書き出しと結びのあいさつを入れるだけで印象がぐっと良くなります。
「ていねい・短く・具体的に」——この3点を守ることで、先生も安心して対応できます。
書き方で差が出る!伝わりやすい工夫とNG例
同じ内容を伝える場合でも、書き方ひとつで印象や伝わりやすさが大きく変わります。
ここでは、先生にとって分かりやすく、丁寧に感じられる連絡帳の書き方を紹介します。
「伝わる書き方」は、誤解を防ぐだけでなく、日常の信頼を積み重ねる力になります。
よくある間違い(理由が曖昧・時間抜け・お迎え不明)
連絡帳で多いミスは、「伝えるべき情報が抜けている」ことです。
特に時間やお迎えの情報がないと、先生が対応に迷ってしまいます。
| 間違い例 | 改善例 | ポイント |
|---|---|---|
| 今日は帰ります。よろしく。 | 本日〇時頃に早退させていただきます。お迎えは母が伺います。 | 時間とお迎えを明記することで正確に伝わる。 |
| 家庭の事情で帰ります。 | 家庭の都合により〇時間目終了後に早退させていただきます。お迎えは父が伺います。 | 「いつ」帰るのかを具体的に書く。 |
短くても、3つの基本情報(理由・時間・お迎え)は必ず入れるようにしましょう。
NG→OKで比較する「印象が良くなる言い換え集」
ほんの少し言葉を変えるだけで、柔らかく、丁寧な印象に変えられます。
| NG表現 | OK表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 今日は帰らせます。 | 本日早退させていただきます。 | 依頼の表現に変えることで丁寧さが増す。 |
| 〜で帰ります。 | 〜のため、早退させていただきます。 | 理由を入れることで誤解を防ぐ。 |
| よろしくです。 | よろしくお願いいたします。 | 敬語を整えることで信頼感が生まれる。 |
上記のOK表現は、連絡帳だけでなく、他の保護者連絡にも応用できます。
書き方の印象=相手への気配りだと意識すると、自然と丁寧な言葉が選べます。
書くタイミング・連絡の順番の正解
早退の連絡は、書くタイミングや伝える順番でも印象が変わります。
以下の流れを意識しておくと、先生が読みやすく、対応しやすくなります。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① あいさつ | いつもお世話になっております。 | 冒頭のひと言で丁寧な印象を作る。 |
| ② 要件 | 本日〇時頃に早退させていただきます。 | 具体的な時間を先に伝えると分かりやすい。 |
| ③ 補足 | お迎えは母が伺います。 | 先生が確認しやすい情報。 |
| ④ 結び | お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 | 締めの一言で丁寧に終える。 |
連絡帳は「一読で伝わる」構成を意識すると、印象も対応もスムーズになります。
ここまでの内容を踏まえ、次章では「アプリ・電話連絡との併用」でより確実に伝える方法を紹介します。
より確実に伝える!アプリ・電話との併用法
近年は、学校と家庭の連絡手段が多様化しています。
連絡帳だけでなく、学校指定アプリや電話を併用することで、より確実に早退の情報を伝えられます。
重要なのは「どの方法でも情報の内容をそろえる」ことです。
緊急時に連絡帳が間に合わないときの正しい対応
朝の登校前や授業中に急に早退が必要になった場合、連絡帳だけでは対応が遅れることがあります。
そのようなときは、まず学校に電話で伝えるのが確実です。
| 手段 | 対応の流れ | ポイント |
|---|---|---|
| 電話 | ・学校事務や担任へ直接伝える ・連絡帳にも同じ内容を記載しておく |
口頭+記録で誤解を防ぐ |
| メモやアプリ | ・家庭で記入内容をスクリーンショットまたはメモに残す | 伝達内容を確認できる形にする |
電話連絡のあとに連絡帳へも同じ内容を記すと、先生が記録を取りやすくなります。
アプリ連絡の文面例(Classroom・まなびポケットなど)
最近は、保護者専用アプリで早退を連絡する学校も増えています。
以下は、アプリのメッセージ欄に使えるシンプルな文例です。
| 場面 | 例文 |
|---|---|
| 定期的な早退 | お世話になっております。本日〇時頃に早退いたします。お迎えは母が伺います。よろしくお願いいたします。 |
| 急な用件ができた場合 | お世話になっております。本日、急な家庭の用事のため〇時間目終了後に早退いたします。お迎えは父が伺います。 |
| 再確認メッセージ | 先ほどの件について、早退時間は〇時頃です。よろしくお願いいたします。 |
アプリでは改行や文字数に制限があるため、短く整った文章を意識すると伝わりやすくなります。
「敬語を保ったまま短くまとめる」ことが、読みやすさと信頼感を両立させるコツです。
連絡後にトラブルを防ぐ確認ポイント
連絡を終えたあとも、先生との行き違いを防ぐための確認をしておくと安心です。
| 確認項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ① お迎え時間 | 予定が変わる場合は早めに再連絡する |
| ② 迎えの場所 | 玄関や昇降口など、先生と共有しておく |
| ③ 記録 | アプリや連絡帳に同じ内容を残しておく |
学校側も安全確認を重視しているため、情報の一貫性がとても大切です。
どの手段を使う場合でも、同じ内容を正確に伝えることでスムーズな対応が期待できます。
「電話+連絡帳+アプリ」の三重チェックを意識すると、ミスを防ぎやすくなります。
次の章では、先生との信頼関係を深めるためのちょっとした工夫を紹介します。
先生への信頼を深めるために大切なこと
早退の連絡は、単なる事務的なやりとりではありません。
丁寧な書き方やちょっとした配慮を心がけることで、先生との信頼関係をぐっと深めることができます。
「きちんと伝える姿勢」そのものが、学校との良い関係づくりの第一歩です。
家庭で共有しておく早退ルール
家庭内で早退の流れを共有しておくと、いざというときにも落ち着いて対応できます。
特に共働き家庭では、誰がどのタイミングで連絡を取るかを決めておくと安心です。
| 項目 | 家庭で決めておくこと |
|---|---|
| 連絡担当 | どちらの保護者が学校に連絡するか |
| お迎え担当 | 誰が迎えに行くか、代わりの人は誰か |
| 連絡内容 | 時間・場所・理由をそろえて伝える |
こうしたルールをあらかじめ決めておくだけで、連絡ミスや混乱を防ぐことができます。
先生が確認しやすい連絡は、子どもの安全にもつながります。
お迎え時に注意すべきマナーと伝え方
早退時のお迎えは、学校との接点のひとつです。
短い会話でも、明るくていねいなやり取りを意識しましょう。
| 場面 | おすすめの言葉 |
|---|---|
| 迎え時の声かけ | 「お忙しいところ、ありがとうございます。」 |
| 帰り際 | 「ご対応いただきありがとうございました。失礼いたします。」 |
| 伝言があるとき | 「〇〇の件については、後ほど連絡帳に記載いたします。」 |
たった一言でも感謝を添えることで、先生との関係はより良いものになります。
また、口頭で伝えた内容はその日のうちに連絡帳へ残しておくと、記録としても安心です。
書き方ひとつで変わる、学校との関係性
先生は毎日たくさんの連絡帳を目にしています。
その中で「わかりやすく、丁寧に書かれている連絡帳」は、自然と印象に残ります。
| 印象が良い書き方 | 印象が悪い書き方 |
|---|---|
| 整った文字・簡潔な文・敬語が整っている | 急いで書いたような走り書き・略語 |
| 感謝の言葉をひとこと添えている | 要件だけで終わっている |
先生も「きちんと伝えようとしてくれている」と感じることで、信頼が深まります。
早退の連絡は、単なる情報共有ではなく、“信頼を積み重ねる機会”でもあります。
次の章では、ここまでの内容を整理しながら、「早退連絡をスムーズに行うためのまとめ」をお伝えします。
まとめ:正確で丁寧な早退連絡が、子どもの安心につながる
早退の連絡は、単に学校へ知らせるだけのものではありません。
保護者と先生が信頼関係を築き、子どもが安心して学校生活を送るための大切なコミュニケーションのひとつです。
連絡帳は「家庭と学校をつなぐ橋」として、正確さと丁寧さが何より大切です。
この記事で紹介したように、早退の連絡では次の3つのポイントを押さえましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 必要な情報を明確に | 理由・時間・お迎えの3要素をそろえる |
| ② 伝わりやすく | 「短く・丁寧に・具体的に」を意識する |
| ③ 感謝の気持ちを添える | 「お世話になっております」「よろしくお願いいたします」を忘れずに |
また、連絡帳とあわせてアプリや電話を併用することで、より確実に先生へ伝えることができます。
家庭内でも早退時の対応ルールを共有しておけば、いざというときもスムーズです。
ていねいな連絡は、先生にとっても保護者にとっても安心のもと。
そして、それは子どもにとって「見守られている安心感」につながります。
正確で丁寧な早退連絡は、小さな信頼の積み重ねです。
これからも、心のこもった一文で、家庭と学校の絆を育てていきましょう。

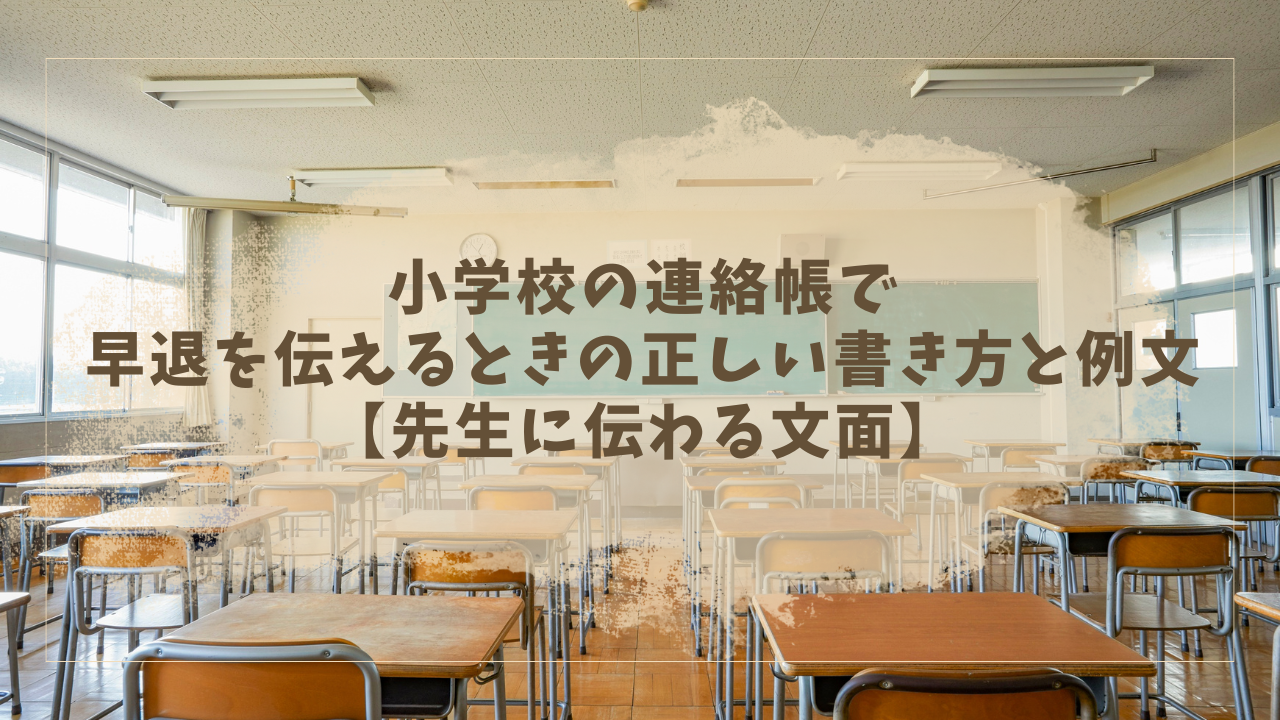
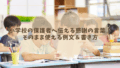
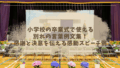
コメント